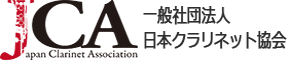お問い合わせ

中高生のQ&A
まず、教える側が焦らないことです。 例えば自転車も、すぐ乗れる人とそうで無い人がいます。最後には全員乗れますが、習得の仕方はそれぞれ。特に楽器は複数の動作の連携が大切。
高価な楽器を手にしているだけで緊張しているはず。その上、姿勢、呼吸、唇の形、歯や舌の位置などと言われたらかなりパニックしているはず。
見よう見まねですぐ音が出る人もいますが、そういうマグレでスタートしてしまう方が後々問題が発生しやすくなります。時間をかけて習得した方が結局伸びるものです。途中メモを取らせたり、鏡も利用しましょう。横で一緒に吹いて音や息のスピードを感じ取らせるのもオススメです。
質問を読みましたが手順などはとても良いと思いました。間違ってはいないと思いました。 教える順序ですが、私の場合はまずは姿勢や持ち方等、見えやすいところから指導して、次は腹式呼吸。口の形(アンブシュア)、口の中などは後回しにします。
よくある勘違いに息をリコーダーのようにリードとマウスピースの隙間に入れるものだと思ってしまう人には、「息はリードに当ててこの硬い木片を向こうへ倒そうとしてごらん。その時、下の歯でしっかり押さえておいて」と言ってみてください。フルートもまるーい穴に息を放り込んでも鳴りませんよね。リコーダーの習慣がアダになることがあるので気をつけてみてください。誰でも一発で音が出るイメージは捨ててもらいましょう。
すぐ出来ない事にショックを受けてやる気がなくなるタイプの人には、時間をかけることが悪い事で無いと言い聞かせて。自転車に乗れるまで半年かかった私が自信持って保証します。 またいつでも待っています。
京谷麻里子
こんにちは。質問にお答えします。初めてのコントラバスクラ大変ですね。
学校の備品だと思いますが、この楽器はとても重く大きいので、まず組み立て時や楽器を置くときに注意しないとkeyを曲げてしまうことがよくあります。リードミスが鳴ってしまう一番の原因はまず、「キーのバランスが崩れる事で出来てしまった隙間」次に、「アンブシュアがうまく作れずにひっくり返ってしまう」が考えられます。解消するためにできる事ですが、
①修理の専門家に見てもらう。
②スムーズに鳴る音のロングトーンをしつこくやって始めて口の締め方と息の向きを掴む。追加のチェックとして、この楽器のkeyは大きいので③押さえている指の位置の確認(なるべくセンターが良い)もしてみてください。
ずっと保管されていた楽器は調子が狂っていることが多く、息を通していくうちよくなることもあります。 また、 原因が楽器であることを確認する方法として他の人が吹いても同じ現象になるかを確認すると良いです。
私もこの楽器を初めて吹いたときに大いに音がひっくり返りましたし、視界が揺れたり、鼻が痒くなり、驚きました。しばらくすると慣れました。そして、地を這うような痺れる低音が今は大好きです。
京谷麻里子
クラリネットとあなたがいつも離れない場所はどこでしょうか。
マウスピースと、右手親指なんです。他の指はついたり離れたりしています。
その右手親指で楽器を持ち上げて口の中にマウスピースを入れてみてください。その時に下唇と上の前歯でマウスピースが全部入るのをとめることができますか?下側にはリードがついていて、息を当てて振動させなくてはならないのでどちらかというと上の前歯を基準にしっかり親指と支え合う感じでしょうか。
だから前歯を当てなくてはならないのです。
丁度初めて自転車に補助輪なしで乗れた解放感と似ているバランス感覚です。
次にマウスピースを咥えずに、イメージはそのままで口を緩めた状態から少しずつ口の両側から締めてみてください。
だんだん息の音がすきま風のように聞こえてきませんか?同じことを指を押さえない開放のソの音を出すつもりでマウスピースをくわえて前歯と親指で楽器を支えた状態で息を出しながら口の両側を締めてみてください。音が出るはずです。自分の音を聞きながらまっすぐ気持ちよくソの音が出たらバッチリです。
10人いたらみんな歯並びも身体の大きさも違います。お友達と違う歯の場所だったり唇の感じが違っても気持ちのよい音が出ていたらバッチリです。唇は買ったばかりの柔らかいゴムホースのようにマウスピースの回りを柔軟に包みこむ感じかな。唇よりも音がまっすぐ出ているかを一生懸命聴いてください。
楽器は音の出る道具です。最初に話したしくみがわかればきっと上手に道具を使えるようになりますよ。
藤井洋子
質問ありがとうございます。
「遠くに音を飛ばすイメージで音を出そう!」 良く使われますね。
でもイメージと言われてもなかなかつかみにくかったり、どうしたら良いか分からないことがありますね。 イメージを持つことはとても大切です。 でも漠然とイメージをするのではなく、イメージ=意識=意思と感じましょう。
お友達と(佳純ちゃんとしましょう)向かい合わせに座って佳純ちゃんの名前を呼ぶときと隣の教室のドアから出てきた佳純ちゃんの名前を呼ぶとき、体育館の奥に立っている佳純ちゃんに振り返ってもらいたい時にかける「佳純ちゃん」の声はそれぞれ違いますね。
声の大きさ、言葉の発音、声を出す方向、声の出し方など佳純ちゃんが遠くにいればいるほど変わってきますし、こちらを向いてほしいと思う意識が強くなります。 まず声の大きさが大きくなります。 遠くに声を届かせるためには声を大きくするだけではなく、声をしっかり出しますね。
言葉の発音もはっきりしゃべります。 佳純ちゃんが近くにいるときにはもごもご話しても通じますが、距離が離れるにつれ「か・す・み・ちゃ・ん」と一言一言はっきり発音しますね。
声を出す方向 遠くにいる佳純ちゃんに声を届かせるためには声を上向きに出して遠くに飛ばします。
声の出し方 ただ喉から大きな声を出すのではなく、体全体を使って声を飛ばすように出します。「か・す・み・ちゃ・ん」の一言一言の声、息をしっかり体で支えて声を出します。 山に向かって「ヤッホー!」と叫ぶときには喉を広げて一つ一つの言葉をはっきり発音して、声をおなかで(みぞおちのあたり)しっかり支えていますが、それ以外の体の力は抜けているんです。試してみてください。
これをクラリネットに置き換えましょう。 遠くにいる佳純ちゃんに音を届かせるためには、届かせる方へ意識を向けて音を出しましょう。 音を上向きに飛ばすためには、出した音の音色や音程が不安定にならないように音をしっかり支えてのびのびと吹きましょう。大きな音を出そうと体に力を入れすぎるとかえって音に伸びがなくなってしまいます(ヤッホー!の感じで体の余分な力を抜いて音を伸ばしましょう) 「か・す・み・ちゃ・ん」の一言一言をはっきり発音することをクラリネットに当てはめると、アーティキューレーションをはっきり吹きましょうということになります。 スタッカート、スラー、いろいろなアーティキュレーションがありますね。 それぞれの違いをスラーは滑らかに、アーディキュレーションが付いている音符はリズミカルに明確にはっきり演奏すると音の一つ一つが伸びやかになります。 目線を上に向けて音を出すだけでも出る音は伸びやかになるんですよ。
「イメージ」することを身の回りに置き換えて「意識」すると意思が生まれて実践に繋がります。
P→クレッシェンド→f→デクレッシェンド→Pのロングトーンをいろいろな音で、pの音量の時は近くにいる佳純ちゃんにきれいな音を聴かせるように、クレッシェンドがかかるにつれて離れていく佳純ちゃんに美しい音を届けるように、fになったら遠くにいる佳純ちゃんに美しい音をプレゼントするようにしっかり上記のことを参考に意識、実践してロングトーンをやってみてください。
きっと美しく遠くへ伸びる音色になりますよ! 遠くに届く美しい音を目指してがんばりましょう!
新井清史
バスクラリネット、豊かな音色と表現力豊かな魅力がいっぱの楽器ですね♪
それだけに音程が不安定になると気になってしょうがなくなってしまいますね。 音程は、それぞれの楽器個体が持っている癖のようなものもありますし、マウスピースと楽器の関係から生じるもの、アンブシュアから生じるものなどがあります。
ドイツ音名LowDと中音域のC.C#が低く、管を抜くと下第一線のB♭あたりが低くなるということですが、音程が低い場合は管を抜くことはないと思います。 もしかして「管を入れる」の打ち間違いかも知れませんね。 もしも入れた時に下第一線のB♭あたりが高くなってしまうようでしたら、上管と下管の繋ぎ目を少し抜いて(そのままだと上管の重みで隙間がふさがってしまうので間に厚紙などをはさんでみる)音程を調整してみると良いかも知れません。
特殊管一般的に言えることですが、何かしらの音程が不安定になるということは多いです。
低い音程を無理に上げようとするよりも、高めの音程を響きを出して低めにする方が全体的に音程の調整は楽です。
アンブシュアの柔軟性を高めることを意識して練習しているのはとても良いですね。 ただ、アンブシュアの柔軟性を求めて音程を組み立て用とすると音色や響きを犠牲にしてしまう恐れもあるので、アンブシュアをしっかり固定して息の柔軟性を高める練習もすると良いです。
音程が不安定な箇所も息の流れ、支えなどで、その音1つの音程ではなく流れやまとまりの中での音程を作る練習をすると良いと思います。
まずは、ロングトーンで音色を安定させるようにします。 そしてスケール練習。 息の流れ、方向、音色が均等になるようにスケールを良い音で、良く響かせて練習しましょう(いろいろな調で) 息を効率よく使って良い音色で滑らかにスケールを吹くことで音の繋がりと2度の音程感覚を良くします。 そして、インターバル練習。 CDurで三度C→E、D→F、E→G、F→A、G→H、A→C、~~~→下がる時も GDurで三度G→H,A→C,H→D,C→E、D→F,E→G、~~~~~→下がる時も CDurで四度C→F、D→G、E→A、F→H、G→C、~~~~→下がる時も 以上を応用していろいろな調で練習しましょう。 この練習をすることによって、アンブシュアを安定させるとともに音が離れた時の音程感覚を養うことができます。
音程が不安定だと、どうしても不安定な音程に意識が行きがちになってしまいますが、音の流れの中や音と音の跳躍の幅の音程を感じるように練習すると不安定な音程に対しての対処する1つの方法になります。
まずはこの練習で頑張ってみてください。 う~~~ん、、、、、頑張ったけど、まだまだダメだぁ、、、 となった時には遠慮しないでまた相談してくださいね。
大好きなバスクラリネットの魅力を十分に発揮できるように頑張ってください! 応援してます! またいつでも質問してください。
新井清史
痛い音とはキツイ音のことかな?
エスクラは飛び抜けて聴こえる音域だしそういう役割なのですが、実はそんなに頑張らなくても聴こえるんです。一生懸命吹きすぎると自分の音しか聴こえなくなってしまいます。誰と一緒かな、誰とハモっているかなと回りの音を一生懸命聴いてみてください。自分の音と回りの音たちと仲良くなれればいつの間にか気持ちいい音色で吹けるようになりますよ。頑張ってね。
藤井洋子
1.正確さを重視:タンギングを行う際には、速さを目指すよりも、正確さに意識を集中することが大事です。速さだけを追求すると、音の品質が犠牲になることがあります。
2.タンギングの種類:音を止めるタンギングと音を切るタンギングの2種類を練習するとよいでしょう。これにより、演奏の幅が広がり、表現力が豊かになります。
3.口の中と舌の位置:タンギングを行う際には、口の中での舌の位置、およびマウスピースもしくはリードのどの位置を舌が触っているかを意識することが重要です。これにより、音のクリアさとコントロールが向上します。
4.アーティキュレーション:アーティキュレーションの正確さを意識することが、速いタンギングにつながります。音の始まりを明確にし、各音をはっきりと区別させるようにしましょう。
5.楽しむこと:クラリネットは美しい楽器であり、演奏を楽しむことが大切です。練習に励みながら、音楽との出会いを楽しみ、充実したクラリネットライフを送ってください。
これらのポイントを意識しながら、コンスタントに練習を積み重ねることで、タンギングの技術が向上することでしょう。練習頑張ってください!
大和田智彦
質問ありがとうございます。
タンギング、難しいですね。 きれいなタンギングができると気分が良くなりますが、上手くできないと妙に落ち込んだりします。 タンギングを上手にするアプローチの仕方はいろいろありますが、以下に書くことを1つの練習方法として試してみてください。
タンギングは音を区切ったり、音を発音するきっかけを舌で行います。 きれいにタンギングを発音するために舌をリードに当てる位置や動き、強さなど舌に意識が行きがちになるのですが、まず良い音を出すことに重点を置きましょう。 出した音が不安定だったり、しっかり音を息で支えられていないとタンギングをした時に舌と息のバランスが悪くなって上手くタンギングができなくなりますので、ロングトーンをしっかりやってしっかりした息で音をコントロールできるようにしましょう(p、mf、fなどいろいろな音量や音の高さ)
長く伸ばした音を舌を使って短く区切ったり滑らかに発音したりするのですが、まず声を出して「ラーラーラー」と言ってみてください。 舌が、上あごに触れたらすぐに離れますね。 この時声(息)はずっと一定の圧力と早さで出たままになっています。
次に声を出して「タッタッタッ」と言ってみましょう。 「タッ」と発音する時の小さい「ッ」では舌が上あごに触れたままになっていて息の流れを止めています。
大まかに言って、この2つの種類の舌の使い方でタンギングをするイメージで良いと思います。
「ラーラーラー」と「タッタッタッ」と発音する時に上あごに舌を触れますね。 クラリネットでタンギングをする時は、リードを上あごに置き換えて舌を触れます。
クラリネットを吹いて音を伸ばしたまま、上記の「ラーラーラー」と「タッタッタッ」を吹いて発音してみましょう。 きれいなタンギングにするために、ゆっくりと自分の音を良く聴きながら発音しましょう。 自分が出せる良く響かせた良い音を出しながら上記の発音をして、発音する時の音色が一定になるよう(ロングトーンの音と同じような音色になるように)練習しましょう。
メトロノームを使ってゆっくりしたテンポ(♩=60~)から音を確かめながらテンポを速くしていきましょう。
舌に力が入りすぎているときれいな発音になりませんので「ラーラーラー」の場合は舌をリードに触れる程度で、「タッタッタッ」はリードの振動を止めるだけと意識してみましょう(もちろん音が大きくなればリードを止めるために力は必要ですが、力を入れすぎないようにすることが大切)(力を入れすぎると速いタンギングができなくなります)
タンギングを取り入れたスケールの練習をすると良いです。 まずスラーでスケールを吹いて同じスケールをリピートした時はスタッカートで吹くなど、スラーとタンギングをマスターするためにはスケールを練習する時にいろいろなアーティキュレーションで練習しましょう。 スラーでスケールを吹いた時とタンギングをした時の音色が同じになるように自分の音を良く聴いて練習しましょう。 スケールもいろいろな音量で練習しましょう。
いろいろなアーティキュレーションを取り入れたスケールを練習することによって息と舌の関係が良くなり、タンギングが美しく確実になります。 タンギングを確実なものにする近道があれば良いのですが、クラリネットの他の奏法と同じく近道はなく継続的に繰り返し練習する他に道はありません。 でも、繰り返し練習することによって、ある日突然道が開くことがクラリネットを練習する上で多々あることですので、あきらめずに頑張って練習してください。
新井清史
こんにちは。
サイドキーの上から2番目のキー(B♭トリルキー)がぐらついているとのこと、心配ですね。 クラリネットのキーは楽器に対して上下に動いてタンポでトーンホールを塞いだり開けたりするので横にぐらぐら動くことはありません。 実際に楽器を見ていなので原因は分かりませんが、
①キーポスト(キーと楽器をネジで止めるために付いている丸い突起物)とB♭トリルキーを止めるネジが緩んでいる。 1つのキーを動かすために2つのキーポストが楽器には取り付けてあるのですが、 ②B♭トリルキーのための2つのポストキーの間隔が広がってしまっている。 ③ポストキーの穴が広がってしまって、B♭キーのネジが動いてしまいキーも動いてしまう。 などなどネジのゆるみに問題があるかどうか見てみましょう。 サイドキーを横から見ると、キーを止めてあるネジが見えますので、緩んでいないか確かめてください。
B♭キーを楽器に対して横に軽く動かしてみて(軽くです)、キー全体がカコカコといった感じに動いてしまうようでしたらキーポストが広がってしまっているのかも知れません。 キーの動きが滑らかになるように、キーとキーポストの間には微妙な遊びが作ってあるのですが(遊びがないとキーが固まって動かなくなってしまう)、はっきりと動いてしまうようでしたらキーポストに原因があるかもしれません。
キーが横にぐらぐら動いてしまうと、トーンホールを塞ぐタンポの位置がずれてしまうこともありますので、楽器店でみてもらうことをおすすめします。 上管のB♭トリルキーやCトリルキー(サイドキーの1番上のキー)は、キーの長さが長いので調整がしっかりしていないといろいろな不具合が出てしまいます。
楽器店でみてもらって直してもらいましょう。 「なんだ、こんなことが原因だったのか」ということもありますし、「みてもらって良かった♪」ということが多々あります。
楽器の調整を怠ると演奏中に突然音が出なくなってしまうこともありますので、この疑問を良い機会だと思って楽器店で調整してもらうと安心して演奏することができます。
良い状態の楽器で思いっきり楽しく演奏しましょう!
新井清史
こんにちは。
50万円程度のクラリネットは ヤマハだとYCL-CEVmaster、YCL-CSVmasterの2器種。 セルマーだとプロローグ GENERATION2。 クランポンだとGALA、E13の2器種。R13もありますが60万円を超えてしまいます。 バックーンだとGrenadilla B♭。
以上6器種が40万円台から50万円台で購入できるクラリネットです。 クランポンのR13がセールで50万円台になっているところがあるかも知れませんのでいろいろ調べてみてください。
各メーカーそれぞれに魅力的で、音色に関してもそれぞれのメーカーごとでの持ち味がありますので、できれば各メーカーのクラリネットを吹いてみてご自分にしっくりくる楽器を選ぶと良いと思います。 息がスムーズに楽器に入り、自分の好みに合った音色が出る楽器を選ぶと良いと思います。 もしもご自分で選ぶ自信がなかったら少し価格が高くなってしまいますが、プロが選んだ選定品を購入するのも良いです。 高校を卒業してもクラリネットを続けられるとのこと、良い楽器と出会えると良いですね。 頑張ってください!
藤井洋子、新井清史
◯ クラリネットを上手に演奏するためには、三つの事を同時進行で考える必要があります。
・息
・指
・舌
の三つです。 これらが頭のなかで独立して考えられ、別々にコントロールできることで、良い演奏に繋がります。
まず、タンギングのコツについて確認しておきましょう。タンギングをするときは「息を流し続ける」「息の圧力を抜かない」ことが大切です。ロングトーンの息を舌で止めて行きますが、舌がリードについて音が止まっている時も、常に息の圧力がかかっている事が大切です。
水が出ているホースの先を手で押さえて水を止めると想像してください。手で押さえると水は止まりますが、水の圧力は手まで来ているので、手を離すとすぐに勢いよく水がでますね!この「水」が「息」、「手」が「舌」です。これを実現するには、頭の中で「息」と「舌」を別々に意識して、舌を動かす時も常に息を流し続けるのです。息と舌が連動してしまっていると、舌が動くと途端に息が止まってしまう…ということが起きます。
さて、あなたの場合、同じ音の時は顎が動かないとのことなので、「息」と「舌」の関係は上手く行っているのだと思います。ここに「指」が入ってきたとき、「息を流し続ける」ことに支障があるのではないでしょうか? 顎が動く人は、太い息の柱を忘れて口先の勢いだけで「ファッファッファッ…」とやってしまう人が多いようです。
練習方法としては、まず低いドの音で何回かタンギングして(そのとき顎は動かないはず)、そのままドレミファソ〜と指を変えていきます。そのとき意識するのは「息」です。同音でタンギングしていた時と全く同じ息の入れ方ができているか?そして次はレから、レレレレレミファソラ〜、ミミミミミファソラシ〜という風に、まずは簡単な指遣いで、指が動いても息が止まらない吹き方を覚えましょう。鏡を見て顎が動かないか確認しながらやると良いと思います。それが習慣になると、難しい事を吹く時も息を流し続けることができるようになると思います。
頑張ってください!!
大浦綾子
高いドの音程が少し低くなるのは割と多くの楽器に見られる傾向です(私の楽器もそうです)。 レジスターキーのトーンホールの大きさを調整する方法もありますが、少しハードルが高いと思われます。
バレルを上管に完全にはめ込んでしまうと開放音域がとても高くなってしまうのでバレルはある程度抜いておく必要があります。
ですのでドの音の音程を上げるにはキィを足して押さえると良いです。
①Gis/Disキィを足すと少し上がる
②Cis/Gisキィを足すと①よりも高くなる
③Es/B♭キィを足すとかなり高くなる
この3パターンが考えられます。 ドの運指にこれらのキィを足してみて自分の楽器の適正な音程を探ってみて下さい。
これらを速いパッセージで使うのは難しいですがロングトーンなどの際には正しい音程に補正できます。
有馬理絵